かすむ実像:男女共同参画社会 (その2) 科学技術における正しい積極的是正措置:大学入学定員男女同数化のすすめ
<異様に少ない女性研究者>
平成17年度版の男女共同参画白書は、科学技術における男女共同参画を大々的に取り上げている。資源小国の日本は、科学技術立国を国是として掲げ、知識ベース産業社会の実現を目指しているものの、皮肉なことにその要とも言うべき研究開発を担う人材ストックは、少子化と理科離れという二重苦にあえいでいる。今日の状況を放置すれば、近い将来に大幅な人材不足に陥ることが予測されており、その打開の切り札の一つと目されているのが、眠れる人的資源、すなわち女性の活用なのである。
日本の総研究者数は現在約83万人(2005年)[1]であり、これは労働力人口 1 万人当たり129 人 に相当する[2]。1980年には、今の半分の 1 万人当たり64人(総数約36万人)[3]であったが、毎年右肩上がりで増加し今にいたっている。現在では働く人100人に1.3人が研究者という、まさしく研究大衆化の時代に突入している。1980年以降増加した47万人に上る研究者の実に7割は、産業界が創出した新規雇用であり、このことは我が国が知識ベース産業社会に着実に近づいていることを物語っている。産業界のなかでも研究者の大半を抱える製造業だけに限れば、従業員10人のうち1人が研究者となっている。
研究者の質・量両面での更なる向上が求められるなかで、少子高齢化、人口減少、理科離れに抗して、このトレンドをどこまで維持できるのだろうか。我が国の研究者のうち女性研究者が占める割合を見てみると、過去10年にわたって僅かずつ増加してきているものの、ようやく11.9%に達したに過ぎない[図1]。全産業でみると、女性就業者が少なくとも数の上では40%を占めることを考えると、11.9%という数字は、科学技術が、突出して女性進出が遅れた分野であることを示している。
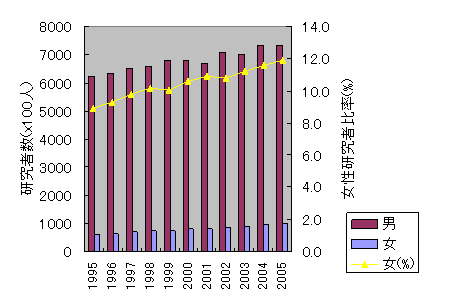
図1.研究者数の年次推移と女性比率
平成17年科学技術研究調査より作成
国際的にもこのことは明らかで、米国(33%)、イギリス(26%)にも遠く及ばず、先進工業国では最下位と言ってよい惨状である。女性の労働力率が46%(就業者の女性比率は約30%)と、日本よりも女性の社会進出で遅れているイタリアでも、研究者の28%が女性であり、他の分野と同等の水準にある。つまり、イタリアでは研究も普通の職業なのに、我が国では研究は女性が参入しにくい(したくない)特殊な職業なのである。ちなみに、職業としての研究の特異性指数を、RA=1-(研究者における女性比率)/(全産業における女性比率)で定義してみると、日本はRA=0.7に対して、アメリカはRA=0.2、イギリスはRA=0.27、イタリアはRA=0.07、男女共同参画の優等生として有名なノルウェーはRA=0.34であり、研究における日本の異常性が浮かび上がる。平成17年度版の男女共同参画白書が科学技術を特集した意図も、この辺りに読み取ることができるのである。
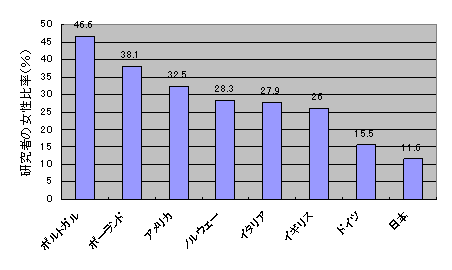
図2.研究者の女性比率の国際比較。日本、アメリカは2004年のデータ。ノルウェーは2001年。ドイツ、イギリス、ポーランドは2000年。ポルトガルは1999年。
男女共同参画白書平成17年度版 第1-序-15図より抜粋
<男女共同参画学協会連絡会の提言>
それでは、研究を普通の職業にするにはどうすれば良いのだろうか。科学技術への女性の参加を高める必要性は、国内学会でも早くから認識され、平成12年12月「男女共同参画基本計画」閣議決定を受けて、平成14年には応用物理学会、日本化学会、日本物理学会などが音頭をとって理工学系学協会に呼びかけを行い、12学協会が参加する男女共同参画学協会連絡会を発足させた。連絡会は、アンケート調査を実施したり、シンポジウムを開催するなどの活動を通じて、平成16年には、「研究助成への申請枠拡大に関する提言」を公表し、非常勤研究者への研究費助成の拡大(女性が育児負担で常勤職に就きにくい現状に基づいて)や、女性科学技術研究者の育成を目指しているプロジェクトを積極的採択、を求めている。平成17年4月には総合科学技術会議に対して「第3期科学技術基本計画に関する要望‐男女共同参画社会実現のために‐」を提出した。要望は、
1.「科学技術分野における男女共同参画モデル事業制度」の創設
2.女性研究者・技術者の採用と昇格に対する数値目標の設定と特別交付金
3.男女の処遇差を低減するための具体的施策
4.育児支援の具体的施策の推進
5.女子学生の理工系学部進学へのチャレンジ・キャンペーンの推進
の5項目からなっており、その骨子はいわゆる積極的是正措置(Affirmative action, Positive discrimination, Positive action)の必要性を認めた上で、社会、制度を数値目標も示しつつトップダウンに変革していくことを要請するものとなっている。例えば、「男女共同参画モデル事業制度」としては、”文部科学省科学技術振興調整費で参加研究者の中の女性が占める割合が30%を越えるプログラムを一定割合で採用する”ことや、採用、昇格に関して数値目標を設定し、評価基準を公開することを求め、”女性研究者割合が一定比率を超えた機関に特別交付金を与える”という報償を提案している。これを受けて、現在、検討の最終段階に入っている第三次科学技術基本計画にも、女性研究者を25%にするという数値目標が盛り込まれようとしている。
このような女性研究者へのあからさまな利益誘導と逆差別的措置が、本当に女性の研究への進出を促進するとどうして言えるのだろうか。この要望の基礎となったシンポジウムの議論や提言を見るかぎり、女性研究者が抱える研究上や生活上の日常的問題を解決することが、女性研究者の増加につながるという短絡的で底の浅い議論しか行われていない。アンバランスな現状を作り出した社会的・文化的・歴史的事象を客観的に分析し、問題の本質を追究して根本的な解決策を構築するという、科学者、研究者に相応しい冷静な姿勢が見えないのである。また、逆差別をナイーブに捉えていてその法的妥当性に対する真摯な検討も見られない。要するに、既に研究者になっている(あるいはその門前に迫っている)女性を、積極的是正措置により優遇することこそが、日本の貧弱な女性研究者層の問題を解決するのだ、という独善的な主張でしかない。その背後には個人の鬱積した不満や怨念の無闇な一般化ばかりが透けてみえて、主張の正当性の論理があまりにも希薄なのである。この議論のずさんさは、学会においてすら、男女共同参画には誰も異議を挟めない雰囲気が反映しているのではないだろうか。
<正しい積極的是正措置>
ここで再確認しなくてはならないことは、性差別のない機会均等が保障された社会制度のもとに、研究が男女両性から普通の職業とみなされ、実態がそれを反映したものとなる、それが当面の日本社会の目標ということだ。数値目標や一方の性の優遇を含む強い積極的是正措置は、このような社会を実現するための時限的な強権施策ではあり得ても、それは恒久的に是認されるものではない。公民権運動やウーマンリブを通じて、30年以上におよぶ積極的是正措置の歴史を持つアメリカは、一般市民、学校、職場から州政府、連邦政府、最高裁まで、多角的で深い論争と、その結果として困難なバランスを保ってきた経験を積み重ねて現在に至っている。米国における積極的是正措置の歴史と現状は、Stanford Encyclopedia of PhilosophyおよびThe Affirmative Action and Diversity Project (University of California, Santa Barbara)に簡潔にまとめられている。
積極的是正措置がその内容によっては、両性の平等という基本的人権に抵触する危険性をはらむものであることから、米国では連邦最高裁判断を通じて、適正な積極的是正措置が満たすべき要件として、(1)有効性と(2)公正性が不可欠のものとの考えが定着している。有効性とは、文字通り、男女平等な社会を実態として作るために、その施策が効果的であるかどうかを問うもので、効果がなけば積極的是正措置は正当化されないことを規定するものである。公正性はさらに、(1)非割当性、 (2)代替不可性、(3)柔軟性、(4)時限性、(5)均衡性、に細分される。非割当性とは、例えば、大学の入学定員を固定的に男女50%ずつに設定する、というような枠の割当(quota)を禁止するものである。米国では、このような割当の設定は明確に違法とされている一方で、社会の構成を反映するような数値的到達目標を置くことは合法とされており、大学や企業はその達成に向けて、相応しい能力・適性を有する候補者を積極的に募集する義務を負っている。積極的是正措置(Affirmative action)は、例えば、女性が少ない職種への採用においては女性の応募機会をできるだけ増やすよう可能な限りの努力をすることを意味し、職種が要求する能力・適性がない者を女性という理由だけで採用することを意味するものではない(公平性の観点からかかる逆差別は禁止)。このように、米国の積極的是正措置は、全ての国民の自由と平等という建国理念と整合させつつ、社会に根強く埋め込まれた差別をできるだけ速やかに取り除くための効果的措置を講ずるという点で、常に難しい舵取りを迫られてきた。近年ではとくに米国社会が保守化するなかで、30年に及ぶ積極的是正措置の役割は終わったとして、むしろ逆差別による弊害を指摘する意見が次第に強くなってきいる。しかし今のところ、国民の大勢は、1995年のクリントン大統領演説、"..When affirmative action is done right, it is flexible, it is fair, and it works...Based on the evidence, the job is not done.... We should reaffirm the principle of affirmative action and fix the practices. We should mend it, but don’t end it. ..(積極的是正措置は、正しく行われれば、柔軟で、公平で、有効である。・・・いろいろな証拠によれば、積極的是正措置の目的はまだ果たされていない。..我々は積極的是正措置の原理を再確認し、問題を正さなくてはならない。我々のなすべきは、それを修正することであり、終わらせることではない)"を支持し続けているように思われる[5]。
米国の比較的抑制された積極的是正措置に対して、よりアグレシブな施策で差別撤廃を一気に実現しようとするノルウェーのような急進的な国も存在する。現在、もっとも女性の社会進出が進んだ国の一つとなったノルウェーでは、あえて男女の割当枠を設けて、強制的に男女平等の実態を作り出そうとしている。かねてから法律で求められていた議会や政府審議会における男女がそれぞれ40%以上の議席を占めるという原則に加えて、最近の政権交代の結果として一定規模以上の企業の役員会にも同様の原則が適用されることになった。経済界からは、役員に求められる能力と適性を持った女性が不足しており、これが強制されれば経済の衰退を招くとして大きな反発が出ているが、政府は断固として譲らない姿勢を示している。
米国も決して一枚岩ではなく、積極的是正措置の完全廃止を求める強硬反対派も居る一方で、推進派のなかには、割当枠の設定も迅速な有効性があれば是認されるとのノルウェーに近い立場をとるものも少なくない。我が国が米国流を取るにせよ、ノルウェー流をとるにせよ、最も重要なことは、最大の効果を最小の副作用のもとで得るための借り物でない独自の施策を、日本の固有の社会・文化・歴史条件のなかで創造することである。
<なぜ女性研究者が少ないのか>
さて、日本の女性研究者が異様に少ない理由は何だろうか。男女共同参画学協会連絡会によれば、女性研究者に対する研究予算や昇格、給与などの処遇が不十分なことが第一で、研究と育児の両立のための支援の不足が第二、そして最後が女子学生の理工系学部への進学率の低さ、ということらしい。そして、女性研究者を研究面で優遇し、さらに生活を支援すれば、女子学生にとって研究者が魅力的な職業となって、研究者を志望する女子学生が増えるはず、という理屈である。男女共同参画学協会連絡会が傘下の学協会会員約2万人を対象に実施したアンケート調査「21世紀の多様化する科学技術研究者の理想像」の結果によると、女性研究者が少ない理由として、男女ともに「家庭と仕事の両立が困難」をトップにあげている(男51%、女60%)。次点は僅差で、女性は「男性の意識」(男25%、女49%)、男性は「女性の意識」(男44%、女44%)を指摘。「男性に比べて採用が少ない」という自明な回答も多数をしめている(男33%、女46%)。男女共同参画白書平成17年度版でも同様に、研究者において女性が少ない理由としては、出産・育児・介護等で研究の継続が難しいこと、女性の受入態勢が整備されていないこと、女子学生の専攻学科に偏りがあることが指摘されている。いずれにも共通して、我が国で女性研究者が少ない最大の理由を、家庭生活と仕事との両立の困難さや待遇の不備に求めている。
このことは、現場研究者の日常感覚としては共感できるところもあるが、それが女性研究者の少なさの直接的な原因であるという主張には、正直疑問を感じざるを得ない。女性研究者の境遇を改善すれば、より多くの女性が研究に参入するという考えは、将来の進路をこれから決めようとする小中高生(当事者)の目線ではなく、今の女性研究者の目線からみた幻影に過ぎないのではないか[6]。むろん女性に限らず研究者の待遇改善は、科学技術立国の一環として大いに進めるべきであるが、女性研究者の拡大策としては、江戸の仇を長崎で討つようなものであろう。事実、2003年に実施された「OECD生徒の学習到達度調査(PISA)」によれば、15歳の時点では、数学、科学、問題解決能力に男女差はなく、読解力は女子がわずかに高い。にもかかわらず、小学校から中学にかけて、女子が理数系を次第に敬遠する傾向が意識調査に現れており、高校3年時点までには、研究者、学者、エンジニアなどの理数系職業は、女子の将来の職業イメージの視野から見事にこぼれ落ちてしまっているのである。大学・大学院の理学系、工学系における女子学生の比率が10%からせいぜい20%という状況(図3参照)は、小中高校と続いてきた女子の理科離れの当然の帰結なのである。女性研究者の11.9%という割合は、この延長上にある。
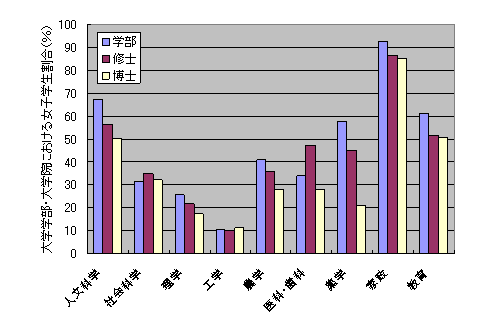
図3.大学学部・大学院における女子学生割合(平成16年度)
文部科学省「学校基本調査」(平成16年度)より[7]
小中高校の女子生徒が理科離れを起こすのは、女性研究者が家庭と仕事の両立に苦労し、十分な研究費を与えられず、昇進も遅いのを見てのことだろうか。小中高校の女子生徒にとって、研究開発の現場などは全く別世界のことであり、いわんや女性研究者がどうであろうが、自分には関係のないことと思うに違いない。女性研究者のロールモデルがないためだとか、研究現場の状況と小中高校の女子生徒の意識を無理やりに結びつける理屈はあるかも知れないが、それは全くマイナーな問題であろう。この視点から、より多くの女子生徒を理科系に向かわせて、研究者になってもらうことを目的とした積極的是正措置として、男女共同参画学協会連絡会の5項目の要請を見たとき、最初の4項目は、今の女性研究者の優遇策以上のものではなく、”正しい積極的是正措置”が具備すべき”有効性”という最初のテストにすら合格できない、お門違いのものであることが明らかになる。
残る「5.女子学生の理工系学部進学へのチャレンジ・キャンペーンの推進」は、女子学生にターゲットを設定したことは正しいと思うが、これとて月並みの感は否めない。長年にわたる理科離れに対処しようと、スーパーサイエンスハイスクールとか小中高生のためのサイエンスキャンプとか、既に文部科学省、学会をはじめとして多くの関係団体がさまざまな施策を行っているにもかかわらず、必ずしも期待されたほどの効果を挙げていないことを考えると、ここで女子学生の理科教育に一石を投じても劇的な成果は望めないであろう。これは長期的視点で地道に継続していくべきことであるが、即効薬にはなりそうもない。眼前の問題から枝葉をそぎ落とし、後に残る焦眉の課題は、結局のところ、大学の理学・工学系女子学生を増やすことであり、これに尽きるのではないか。小中高校と年を重ねるにつれて女子生徒が男子生徒に比して一際速やかに理科離れを起こす原因は、社会全体に蔓延する女子生徒に対するステレオタイプや、いわゆる女らしさの追求をよしとする女子生徒の集団圧力、そして女子に対する親兄弟の特別の期待など、一人一人に内部化されたジェンダーバイアスがその根本的な原因であろう。だからといって、ジェンダーバイアスを目の敵にして立ち向かってみても、砂上に楼閣を作る空しい戦いに違いない。なぜなら、ジェンダーバイアス自身が、社会が生み出す一つの価値観であり、ジェンダーバイアスが絶対的な観念として存在し、社会がその上に作り上げられるものではないからである。ジェンダーバイアスそのものを問題視して、直接対峙することではなく、それを生み出す社会メカニズムを、時代の要請にしたがって変革することのほうが遥かに建設的であり、勝算のもてる試みであろう。
<大学入学定員男女同数化のすすめ>
大学の理学・工学系に女子学生を呼び寄せ、ひいては女性研究者を増加する抜本的な積極的是正措置として、大学の各学部の入学定員を男女同数とすることを提案したい。東京大学を筆頭に、トップ大学が率先して入学定員を男女同数にするのである。男女に割当枠を設定するノルウェー型の極めてアグレシブな積極的是正措置である。学歴・偏差値偏重が根強く支配する日本の小中高校教育の現状をみれば、その効果が如何に劇的であるかは想像に難くない。10年を待たずに、大学自身はもとより、産業界の様相も一変することは請け合いである。もちろん、同数化直後は、もともと女子学生が少ない理学・工学系では、男子にくらべて成績の劣る女子学生も受け入れることになるだろうが、日本人の学歴・偏差値における上昇志向の強さと、そもそも高校初年では男女に理系能力の差がないことを考えれば、3年程度の短時間のうちに、男女の成績は拮抗するようになるに違いない。また、以前にもまして厳しい選別を受けることになる男子学生は、さらに競争が激化するために、少子化による大学全入時代にあっても、学力レベルの維持向上が望めるのだから、一石二鳥というべきであろう。また、トップ大学が男女に同じ広さで門戸を開放することは、女性の社会進出を心理面で後押しする力強い社会的メッセージになるに違いない。
男女定員同数化によって、理工系大学・大学院の卒業生における女性比率は、5年から10年の間で、10%~20%の現状から50%近くにまで、飛躍的に拡大することになる。企業、研究機関、大学における研究者の採用において、優秀な女性科学技術者の応募があまりにも少ないという、科学技術における男女共同参画の致命的な問題点は、これで自動的に解消する。採用はあくまで男女平等に能力本位で行えばよい。男女共同参画学協会連絡会の要望でも、第三次科学技術基本計画(案)でも、女性研究者の採用比率に数値目標と達成期限を設定することがうたわれている。しかし、優秀で意欲ある人材のプールが決定的に不十分な状況を放置したままで、いくら採用枠や期限を設けてみても、それは実質的に達成不可能な目標になるか、職に要求される能力に届かない人材を逆差別的に採用して企業や研究機関の本来のパフォーマンスを阻害したり、研究コミュニティーのモラルや士気の低下を引き起こすという副作用のほうが大きい。さらに、男女共同参画学協会連絡会が要望するように、女性研究者を女性であるという理由だけで予算面で優遇するような研究助成が行われれば、研究という活動が本来的持っている進歩性や独創性という、科学に内在する一元的な価値基準を混乱させ、”女性”をだしに研究費の獲得を狙うような悪行を誘導しかねない。独立行政法人化で外部資金の獲得を至上命題と意識する大学や研究機関の最近の拝金的挙動を見るにつけ、そのような懸念をますます強く抱くのである。現状で、女性採用の数値目標の設定は、いわば枯れかかっている川の水量を増やすために、河口堰を開口するのと同じで、水源を育てて上流の水量を確保しないかぎり、対症療法としてすら成立しない。それでも無理に開門すれば、底に溜まったヘドロが海に流れ出すだけだ。森に木を育てて豊かな水源を確保し、支流への流れを適切に調整して、本流を再生するのが本道というものだろう。複雑に絡み合った社会を相手にする積極的是正措置は、しっかりと急所を押さえて、その後の良い流れが自然に生ずるようなものでなくてはならない。その意味で、男女共同参画学協会連絡会の要望には、とても合格点は与えられない。
大学入学定員を男女同数とすることは、直接的に小中高校の女子生徒に理科への興味を引き起こさせることを狙ったものではない。上記のとおり、このような直接的取り組みは飽和状態に近く、そのターゲットとされる女子学生も実のところ食傷ぎみではないか。入学定員男女同数化は、日本の高い教育熱、とくに有名大学に入ることを学習の目標とするような受験社会の風土をエネルギー源として利用して、理工系学部にも女子学生を呼び込むというレバレージ戦略である。やり方が不純であるとしても、ひとたび女子学生の理工系への流れを作り出し、職業としての科学技術が本来もっている魅力に気づくチャンスを与えれば、その後は自ずとあるべき道が開けることが期待できるのである。それがまた、人事的に閉塞状態にある大学の自己改革にもつながっていくはずだ。
男女平等を実現するために、男女を差別するのは自己矛盾であるという反対もあるであろう。また、入試の成績順に合格者を決めないのは差別だという意見もあろう。しかし、固定化した社会状況を強権的に変革して、新しい時代に即した社会をつくるために、必要最小限の方策として考え抜かれた積極的是正措置であり、男女学生の成績差が無くなれば、自然と消滅する時限的な性格をもったものである。同じ男女割当枠の設定であっても、幼稚園でそれを行ったときに、異議を唱える者はいないであろう。強制的な積極的是正措置を導入するにあたって、できるだけ多くの人が同じ潜在的能力と可能性を持つことを仮定できる若年段階にそれを設定すべきである。既に社会に出た女性研究者を優遇することよりも、大学入学者を優遇することの方が、遥かに社会的害が少なく、合目的で、有効性があるのである。また、税金で運営される国立大学法人における入学者選考の公平性は、必ずしも入試の成績順だけに頼る必要はない。現状でも、AO入試をはじめとして、多様な基準での選考が一般化しているし、もっと基本的に、男と女という社会を構成する対等なパートナーが、応分の教育機会を得るという、成績以外の公平性の基準も大いに理があると思うのである。
積極的是正措置の先進国である米国では、大学・大学院における女子学生割合が、理工系においても着実に高まってきており、それが社会に対する女性研究者の供給源として、良い循環が生まれている[8.9]。過去40年にわたって大学で科学技術(社会科学を含む)を専攻する女性は増えつづけており、現在では、男女ほぼ同数の20万人の卒業生を毎年送りだしている。大学院では女性比率が下がるものの、科学技術での博士号取得者の37%を女性が占めるに至っている。大学院生数では女性が41%となっている。図4に示したとおり、女性大学院生数は、科学技術のどの分野についても増加傾向にあり、とくに工学、計算機科学、生命科学では顕著な増加を示している。これに対して、男性大学院生数は、計算機科学を除く、全分野でわずかずつ減少傾向にある。このように女性の進出は著しく、例えば工学の中でも、従来は女性が敬遠しがちであった電気・電子工学において、1994年から2001年の間に50%もの学生数の増加が見られることは注目に値いする。しかしながら、絶対数でみるかぎり、生命科学については男女が均衡しているのに対して、女性が工学よりも心理学、社会科学をより好み、男性は逆の傾向を根強く持ち続けていることを見て取れる。米国では、大学入試において、女性やマイノリティを対象に比較的マイルドな積極的是正措置を30年にわたって実施した結果として、科学技術への女性進出が着実に進展してきたのである。
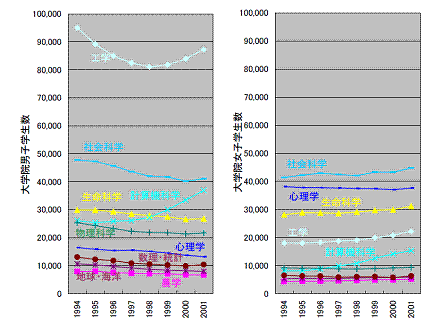
図4.米国大学院における科学技術分野別男女学生数の推移
National Science Foundation(NSF), Women, Minorities and Persons with Disabilities in Science and Engineering, Graduate Enrolment, Female S&E graduate students, by field, citizenship, and race/ethnicity: 1994–2001およびMale S&E graduate students, by field, citizenship, and race/ethnicity: 1994–2001より作成[8]
<エピローグ>
科学技術立国を、男女が協働して支えるようになれば、これまでと全く違う産業社会が現出するのではないだろうか。研究という行為が、無から有を生ずることの喜びに裏打ちされ、全人格をかけた創造作業であり、かつ世界的な競争にもさらされている以上、(一部の識者が言うように)女性研究者の増加がすなわち家庭と仕事の両立を意味するという単純な図式が成立するのかどうか、私個人としては疑問をもっている。しかし、女性の増加とともに、外国人研究者も増加して、研究環境の人的多様化が進行すれば、より闊達で良い意味でのゆとりと奥行きを持った研究文化が実現することも期待できる。これは自由な発想を引き出す良い効果があるかもしれない。職業としての研究の素晴らしさは、知識と物を通じて、社会に貢献する永続的な価値を生み出すことが出来ることであり、それが日本という国の本領に重なるのである。
国際社会で尊敬される"ジャパンブランド"を生み出し、支えてきたのは、トヨタ、パナソニック、ソニーなどの日本を代表する大メーカーや、クラフトマンシップあふれる自転車のシマノなど中堅企業、そしてユニークな技術を持つ無数の中小企業である。不断の技術革新に裏打ちされた優れた品質、国際競争力のある価格、そしてキラリと光る先進的な製品コンセプトを生み出して世界をリードし続けてきた、多くの製造企業と、その経済力が生み出す国際的影響力、そして何より企業を作り上げた人こそが日本の財産である。特徴ある歴史文化や、全体として勤勉で礼儀を重んじる国民性も、国としての品格に一役買っていることも確かである。そこにジャパンスタイルの研究が加わることで、日本が世界の研究文化の交差点にまで成長することを期待したい。
-------------------
脚注、参考文献
[2]我が国の就業者総数6409万人を用いた[労働力調査(速報)平成17年10月結果の概要総務省統計局より]。
[3]「科学技術指標 - 日本の科学技術の体系的分析 -平成 16 年版」文部科学省
[4]女性採用の数値目標を定めるような強い積極的是正措置は、米国ではAffirmative action, 英国ではPositive discriminationと呼ばれる。我が国では、この意味の積極的是正措置をPositive actionと呼ぶこともあるが、米国ではAffirmative actionとPositive actionは異なる意味で用いられており、後者は機会の均等を実現するための逆差別(Reverse discrimination)を含まない施策を指し、前者に比べてより間接的なアプローチをさす。
[5] 我が国には、積極的是正措置の歴史がなく、その経験不足と未熟な人権感覚とがあいまって、物事が国際水準から隔たった脇道に逸れるきらいがある。男女共同参画における積極的是正措置をめぐる論議では、往々にして積極的是正措置が持つ基本的人権の制限や逆差別などの負の側面には目をつぶり、「女性に良いことは誰にとっても良いことだ」をスローガンにした、ナイーブで「目的のためには手段を選ばず」式の暴論が幅をきかせている。世界に類例のない”日本オリジナル”の積極的是正措置ともいえる「女性専用車」などはその好例であって、米国流の積極的是正措置の要件もほとんど満たさないもので、日本社会のお粗末な人権意識を露呈する貧策というほかない。有効性の確保と検証に鉄道会社が全然意欲をもたず行政がそれを放置していることも無責任だが、最も大きな問題は、「女性専用車」が公正性の要件をどれ一つとして満たさないことである。専用車そのものが、1960年代以前の米国の人種隔離を思わせるような完全な”割当性”であり、 車内通報装置・警告装置の設置や、警備員の増強など、より人権に配慮した普通の”代替”手段は無視され、画一的な運用が固定化していて乗客の状況に応じた”柔軟性”はなく、女性専用車が廃止されるための達成目標とその実現手段、タイムテーブル(時限性)もない。また、「女性専用車」による不便は、たまたまその線を利用する男性客、なかでもその車両を利用してきた男性高齢者・身障者に集中的に及ぼされることから、不利益の”均衡性”もないのである。このような時代錯誤の逆差別を許してしまうのも、我が国の貧困な人権感覚にそのルーツがあると言えよう。
[6] 家庭生活と仕事の両立が困難なために途中退職をよぎなくされ、その結果として女性研究者が少ないという面も否定できないが、大学理工系の女子学生割合と、女性研究者の割合が均衡しているという事実は、(女性が研究者として優先的に採用されているという仮定をしない限り)新たな女性研究者人材の供給不足が、根本的な原因であることを示している。
[7]「学校基本調査」文部科学省
[9] The National Academies, Committee on Women in Science and Engineering
